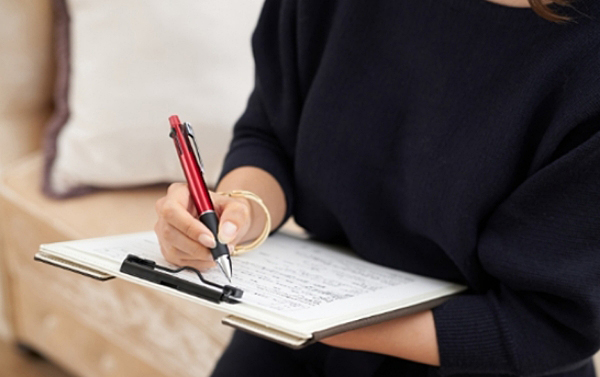ベビーコラーゲン注入治療とは?目の下のクマや細かなシワに効果的!副作用や失敗も解説

美容の悩みを低リスクで、自然な見た目のまま解決できる美容治療と人気のベビーコラーゲン。
本コラムはベビーコラーゲンとは何か、その効果やヒアルロン酸注入との違い、受けるメリットなどを紹介します。
副作用や値段、そして施術を受けて失敗・後悔をしないための方法も解説しますので、ぜひご参考ください。
◆このコラムで分かること
ベビーコラーゲンとは

ベビーコラーゲンとは、Ⅰ型コラーゲンとⅢ型コラーゲンを1:1の割合で配合した、唯一のヒト由来コラーゲン注入剤です。
Ⅲ型コラーゲンは赤ちゃんの肌に多く含まれている成分で、皮膚の柔らかさや潤いを保って細胞の再生を促進する効果が見込まれています。
Ⅲ型コラーゲンは加齢とともに減少してなくなるため、ベビーコラーゲン注入治療は成人後の肌にⅢ型コラーゲンを増やせるとして注目を浴びています。
ベビーコラーゲンの効果

- 目の下のクマを改善
- 細かいしわを改善
- かさつきを改善
- アンチエイジング
1.目の下のクマを改善
目の周りはベビーコラーゲンを希望されるお客様の多い施術部位です。
目の下のクマは凹凸によって生じていることが多く、ベビーコラーゲンで凹んだ皮膚を持ち上げると改善できます。
皮膚の薄い目の周りへの注入治療は不自然な見た目になりやすいのですが、ベビーコラーゲンならプルプルで柔らかいので自然に馴染みます。
2.細かいしわを改善
ベビーコラーゲンは浅く硬いしわの改善に効果的です。
目の周りや額、口元、ほうれい線、首など、さまざまな箇所に施術できます。
施術箇所は弾力性のある、すべすべの肌に変わり、浅く細かなシワは目立たなくなります。
3.かさつきを改善
ベビーコラーゲンを注入した箇所は保湿性が上がり、みずみずい肌になります。
例えば唇へ注入すれば、かさつきが改善されてハリやツヤのあるリップに。
もちろん、加齢によって増えてくる唇の縦じわも目立たなくなりますよ。
4.アンチエイジング
ベビーコラーゲンには細胞の再生を活性化させる働きもあります。
それにより美容効果は長持ちし、アンチエイジングにも高い効果を発揮します。
ベビーコラーゲンとヒアルロン酸の効果の違い
ヒアルロン酸注入も施術箇所をふっくらさせるのはベビーコラーゲンと同じです。
しかし、ヒアルロン酸はベビーコラーゲンよりも粘度が高く、肌のより深い凹凸の改善に高い効果を発揮します。
例えば、深いシワにはヒアルロン酸、浅いシワにはベビーコラーゲンを選択するのがおすすめです。
ベビーコラーゲンのメリット

- 安全性が高い
- 即効性がある
- ダウンタイムが短い
- 人にバレにくい
ベビーコラーゲンの特徴といえば、ヒト由来の成分であること。
それによりどんなメリットがあるか、主なものを4つ紹介します。
1.安全性が高い
ヘビーコラーゲンはヒト由来なため、他の動物から摂ったコラーゲンを注入するのと比べると、安全性がかなり高いです。
感染症の危険なども少なく、アレルギーテストなしで受けることも許されています。
2.即効性がある
ベビーコラーゲンは肌の気になる部位に直接注入するので、効果がすぐに現れます。
施術日からすぐに綺麗になりたい方や、美容治療によくある、効果が現れるまでのもどかしい時間が苦手な方にもおすすめです。
3.ダウンタイムが短い
ベビーコラーゲンは肌に馴染みやすく、注入後のダウンタイムが短いです。
施術して数時間後にはメイクもできます。
施術後すぐに予定がある方、次の日に悪い影響がないか心配な方にもおすすめです。
4.人にバレにくい
ベビーコラーゲンは自然な見た目のまま、美容の悩みを改善してくれます。
顔が大幅に変わったり、不自然な凹凸ができたりする心配の少ない治療です。
美容治療を受けたと周りに知られたくない人も安心して受けられます。
ベビーコラーゲンの副作用、デメリット

- アレルギー反応が起こる可能性がある
- 効果の持続期間が永久ではない
- 余計な凹凸やしこりができる可能性がある
美容医療はどの施術においても、100%安全と言い切れるものはありません。
それは安全性が高いと言われているベビーコラーゲンも同様で、もしもやりすぎれば副作用が出る可能性はあります。
施術はあらかじめ副作用が起こる可能性も頭に入れておいてから受けましょう。
1.アレルギー反応が起こる可能性がある
アレルギーテストなしで手軽に受けられるのはベビーコラーゲンの魅力でもありますが、アレルギー反応が起こる可能性が0というわけではありません。
アレルギー反応による症状は、痒みや赤み、腫れなど。症状は施術箇所だけでなく全身に現れるケースもあるので注意です。
- アレルギー反応への対処方法
- 施術を受ける前にアレルギー検査をしておけば、副作用のリスクを軽減できます。
施術後、体に異変が起きた際は担当医師に相談して冷静に対処しましょう。アレルギー反応が起きていた場合は、抗生剤やステロイド外用薬などを使用して治療します。
2.効果の持続期間が永久ではない
注入したベビーコラーゲンは時間が経つと肌に吸収・分解されていきます。
効果の持続期間は施術部位によっても変わりますが、およそ数か月~1年半程度が目安。よく動く部位ほど効き目が短くなりやすいです。
- 効果が薄まることへの対処方法
- ベビーコラーゲンは継続して注入することで、より高い効果をより発揮し続けるようになります。
コラーゲンが常に補われることで、既にあるシワ改善だけではなく、これからできるシワの進行も防げるのでおすすめです。
3.余計な凹凸やしこりができる可能性がある
皮膚の凹みに弾力を持たせ、自然にボリュームアップさせるベビーコラーゲンですが、注入する箇所や量によっては余計な凹凸・しこりができることも。
また、似た治療であるヒアルロン酸注入の場合、入れすぎたヒアルロン酸は薬剤を注入して分解し、仕上がりを修正できます。
しかしベビーコラーゲンの場合、注入後は人為的に分解できないので、自然に肌がコラーゲンを吸収するのを待つしかありません。
- 生じる凹凸への対処方法
- あらかじめ改善したい肌の凹凸をしっかり見極めておき、施術中は変化の様子を見ながら、注入量を慎重に調整してもらいましょう。
またベビーコラーゲンは注入のし過ぎで膨らみすぎたり、仕上がりに満足いかなかった場合でも、自然と肌がコラーゲンを吸収して元に戻っていきます。
ベビーコラーゲン注入治療で失敗しないための方法

ベビーコラーゲン注入治療でよく耳にする失敗といえば、上記で紹介した副作用だったり、過剰な注入によるものです。
同じような失敗をしないためには、まずは自身がリスクを承知しておくことはもちろん、信頼できるクリニック、施術者を選ぶことも重要です。
そのために、行きたいクリニックの評判や症例などはしっかりチェック。
クリニックに行った際も施術前に「こちらの希望や悩みをしっかり聞いてくれるか」「肌のチェックを念入りにしているか」を見て、信頼できるようであれば施術を始めてもらいましょう。
ベビーコラーゲンの値段
ベビーコラーゲン注入治療の値段は、クリニックによってバラつきがあります。
よく言われている目安は1ccあたり10万円以上。クリニックによっては初回を安くしたり、逆に2回目以降を安くしているところもあります。
表参道メディカルクリニックでは、ベビーコラーゲン単体よりも比較的料金を抑えられるベビーコラーゲンブースターという治療も施術しています。
ベビーコラーゲン注入治療は美容の悩みをナチュラルに治せます!
ベビーコラーゲン注入治療は、気になる部位のしわやクマ、乾燥などの症状を改善します。
ヒアルロン酸やボトックスを使用するよりもナチュラルに見た目改善ができ、細かな微調整も利かせやすいです。
しかし、一度入れたら元に戻るまで時間が必要なので、過剰な注入には注意しましょう。
本コラムを読んで、ベビーコラーゲンに興味が湧いた方はぜひ表参道メディカルクリニックへお問い合わせください。疑問や不安にも丁寧にお答えします。
お時間の都合がよろしければ、無料のカウンセリングも行っていますので、ぜひご予約・ご来院くださいませ。
Flow施術の流れ
表参道メディカルクリニックが選ばれる理由
-
1
どこよりも丁寧なカウンセリング

診察するのはカウンセラー・ナースだけではありません。 『医師の診察時間』をしっかりと設けて、患者様のお悩みに寄り添います。
患者様の肌質やライフスタイルにより必要な治療は十人十色です。 不必要な治療はおすすめせず、本当に必要な治療のみご提案します。 -
2
施術者指名制度導入

担当者を確約できないクリニックが多い中、患者様のご要望にお応えして『指名制度』を導入しました。
ご予約の地点で担当する医師や看護師を確約することが可能です。 -
3
芸能人御用達のクリニック

2019年に美容部門立ち上げて以来、口コミが広がり、さまざまな芸能人や著名人の方にご来院頂いております。
当院はどんな方にも安心してお肌をお任せ頂けるように、定期的な院内・院外研修で知識や技術のアップデートを欠かしません。
いつでも妥協することのない美容医療をご提供します。