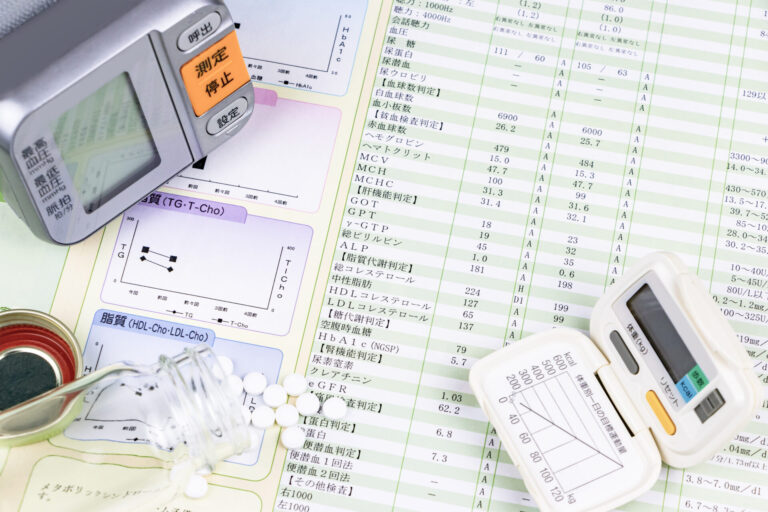肥満について知ろう|基準・原因・種類・健康リスク

肥満は太っているだけでなく、目に見えないところで健康を脅かすような身体の変化が起きている状態です。
このページでは、肥満の基準、原因、種類、健康リスクについて詳しく解説しています。
また、肥満を予防・管理する方法や治療の選択肢についても触れています。
肥満について正しい知識を持ち、健康的な体重管理を目指していきましょう。
目次
肥満とは
肥満とは、日常生活で使い切れずに余ったエネルギー(カロリー)が脂肪として体内に蓄えられている状態です。
一般的には太っている人のことを指しますが、肥満は単に見た目の問題だけにとどまらず、過剰に脂肪が蓄積されてしまうと健康状態に関わることもあります。
そのため、肥満は健康管理が必要な状態と考えられています。
肥満が健康リスクにつながる理由
肥満は太っているという外見上の問題として捉えられがちですが、身体の中では脂肪細胞の炎症により代謝異常を引き起こします。
- 肥満が健康リスクにつながるしくみ
-
過剰な脂肪の蓄積
↓
慢性的な炎症が起きる
↓
さまざまな代謝異常を起こす(糖や脂質、血圧、肝脂肪などの異常)
肥満状態が続くと、脂肪細胞に慢性的な炎症が生じます。
通常は一時的な炎症ですが、脂肪を過剰に溜め込むことで炎症が慢性化しやすくなります。
この慢性的な炎症が代謝異常を引き起こし、生活習慣病をはじめ全身にさまざまな健康リスクが及びます。
肥満の種類

肥満は、脂肪がつきやすい部位によって2つのタイプに分けられています。
内臓脂肪型肥満(腹部肥満)
内臓脂肪型肥満は、ぽっこりと出たお腹が特徴的な肥満です。
シルエットがリンゴに似ていることから「リンゴ型肥満」とも呼ばれ、一般的には男性に多いですが、閉経後の女性にもみられる傾向にあります。
- 内臓脂肪の特徴
-
・蓄えられやすい
・落としやすい
・さまざまなサイトカイン(生理活性物質)を分泌する
内臓脂肪はエネルギーとして利用されるので比較的簡単に落ちますが、だからといって放置するのは好ましくありません。
内臓脂肪から分泌されたサイトカインが代謝異常を引き起こし、生活習慣病のリスクを高める可能性があるためです。
皮下脂肪型肥満
皮下脂肪型肥満は、お尻や太ももに脂肪が蓄積されるタイプの肥満です。
シルエットが洋ナシに似ていることから「洋ナシ型肥満」とも呼ばれ、一般的には女性に多くみられます。
- 皮下脂肪の特徴
-
・時間をかけて少しずつ蓄えられる
・皮膚の表面に近い部分に脂肪がつくので体つきへの影響が大きい
・一度つくと落ちにくい
内臓脂肪型肥満にくらべ、病気のリスクは高くはありません。
しかし、肥満の状態が続くと関節障害や、極端な肥満になると生理トラブルや不妊、さらに閉経後は乳がんの発症に関連があることもわかっています。
肥満の基準
肥満の基準は見た目だけで判断するのではなく、BMI(ボディマス指数)と体脂肪率を用いて判断します。
肥満の程度にはいくつかの段階もあり、肥満度によっては健康リスクも考えられるためです。
それぞれの基準については、次で詳しく見ていきましょう。
BMI(ボディマス指数)
健康診断などでも目にするBMI(ボディマス指数)は簡単に計算できるため、国際的にも広く利用される肥満の指標です。
- BMIの求め方
- BMI=体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))
この計算結果から得られた数値を、以下の表に当てはめてみてください。
| BMI(kg/m²) | 肥満度 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5~25 | 普通体重 |
| 25~30 | 肥満(1度) |
| 30~35 | 肥満(2度) |
| 35~40 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
ちなみに、BMI25以上であることに加え、健康リスクや内臓脂肪の蓄積、検査数値に異常が認められる場合には以下の病気と診断されます。
肥満症
肥満(BMI25以上)であり、肥満による合併症(11種類)のいずれか1つ以上、または健康障害のリスクが高まる内臓脂肪の蓄積がある場合は「肥満症」となります。
また、BMI35以上となると「高度肥満症」となります。
肥満症は健康リスクが高いため、肥満治療の対象となり減量が必要になってきます。
メタボリックシンドローム
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、内臓脂肪が過剰に蓄えられている状態です。
ウエストが男性で85cm以上、女性であれば90cm以上であり、さらに以下のいずれか2つ以上が当てはまる場合はメタボリックシンドロームと診断されます。
- メタボの基準値
-
血圧:130/85mmHg以上
空腹時血糖:110mg/dL以上
中性脂肪:150mg/dLかつ(または)HDLコレステロール:40mg/dL未満
またBMIが25未満であっても、ウエスト径と検査数値が2つ以上当てはまるとメタボリックシンドロームとなります。
この状態を「隠れ肥満」と呼んだりもします。
メタボリックシンドローム(メタボ)について知ろう|診断基準・原因・改善方法
体脂肪率
体脂肪率とは、体に占める脂肪の割合を表したものです。
BMIは身長と体重のみで算出するため、肥満や肥満症を適切に判断するには、どのくらい脂肪が蓄積されているのか正しい評価が必要です。
一般的な体脂肪率の基準については、以下を参考にしてみてください。
<男性>
10%以下:やせ
11~21%:標準
22~26%:軽度肥満
27%以上:肥満
<女性>
20%以下:やせ
21~27%:標準
28~34%:軽肥満
35%以上:肥満
注意点として、上記はあくまでも目安です。
医療機関に相談するきっかけや、ダイエットのモチベーションを高める目安として活用してください。
ご家庭にある体重計では内臓脂肪と皮下脂肪の割合を区別できないため、特に健康リスクの高い内臓脂肪の蓄積を見落とす可能性があります。
また、メタボリックシンドロームの診断基準に体脂肪率は採用されません。
肥満や肥満症の正しい診断を求める際は、医師の診察を受けることをおすすめします。
肥満の原因

肥満は食生活の乱れが原因と考える人が多いですが、実際にはさまざまな要因が重なることで起こります。
環境、心理、遺伝などが複雑に影響し、単に食べ過ぎが原因というわけではありません。
また、明らかな原因がある場合は「二次性肥満」と呼ばれる病気に起因する肥満も存在します。
肥満の健康への影響
肥満により過剰な脂肪が蓄えられている状態が続いてしまうと、やがて健康にも深刻な影響を及ぼします。
わかりやすい例として生活習慣病があげられますが、その他にもさまざまな病気のリスクが高まります。
以下で、肥満症の診断に用いられる健康障害と、診断には含めないものの肥満に関連する健康障害について解説していきます。
肥満症の診断に用いられる健康障害
肥満に関連する健康リスクは11種類あります。
1.耐糖障害(2型糖尿病や耐糖能異常など)
2.脂質異常症
3.高血圧
4.高尿酸血症・痛風
5.冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症)
6.脳梗塞・一過性脳虚血発作(TIA)
7.非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)
8.月経異常・女性不妊
9.睡眠時無呼吸症候群(SAS)
10.運動器疾患(膝や股の関節症、変形性脊椎症など)
11.肥満関連腎臓病
脂肪の過剰な蓄積が臓器や組織に負担をかけてしまい、放置すれば全身に悪影響が及ぶリスクがあります。
場合によっては生命を脅かすこともある深刻な合併症を引き起こしかねないので、単なる外見上の問題として片付けてしまうのは危険です。
肥満に関連する健康障害
肥満症の診断には含まれませんが、肥満によって起こる健康障害には以下のような病気があげられます。
・悪性疾患:大腸・食道・子宮体・膵臓・腎臓・乳・肝臓がん
・胆石症
・気管支喘息
・皮膚疾患:黒色表皮腫、摩擦疹など
・男性不妊
・胃食道逆流症
・精神疾患
肥満に関連する健康障害は、身体だけでなくメンタルヘルスを損ねることもあります。
肥満の予防と管理
肥満は、自己管理によって予防することが可能です。
自己管理の基本は「食事」と「運動」になり、1日のカロリー摂取量を抑えることに加え、運動により消費カロリーを増やすことで減量を図ります。
ただし、いきすぎた自己管理は避けなければなりません。
「○○抜きダイエット」や「絶食」などは、一時的に体重が減少しても、その反動からリバウンドするリスクが高いです。
体重が以前よりも増えることもあるので、長期的に減量するようにしてください。
肥満治療の選択肢
肥満症や高度肥満症、メタボリックシンドロームといった肥満が病的な状態は、差し迫った健康リスクがあるため以下の肥満治療が推奨されます。
- 肥満治療
-
・食事療法
・運動療法
・薬物療法
・外科手術
肥満度に応じて適切な治療方法が選ばれますが、肥満治療も食事や運動による減量が基本となり、必要に応じて薬物療法や外科治療が検討されます。
また、通常の肥満(BMI25以上)であれば、メディカルダイエットが効果的です。
これは美容クリニックで提供されるダイエットプログラムで、ダイエット薬を用いた全身痩せだけでなく、マシンを用いた部分痩せも実現できます。
自己管理が難しい人に適した肥満治療になるので、ダイエットをより効率的かつストレスフリーで行いたい場合には検討してみてください。
メディカルダイエットとは?一般的なダイエットとの違いやメリット・デメリットをご紹介
肥満に対する誤解と真実
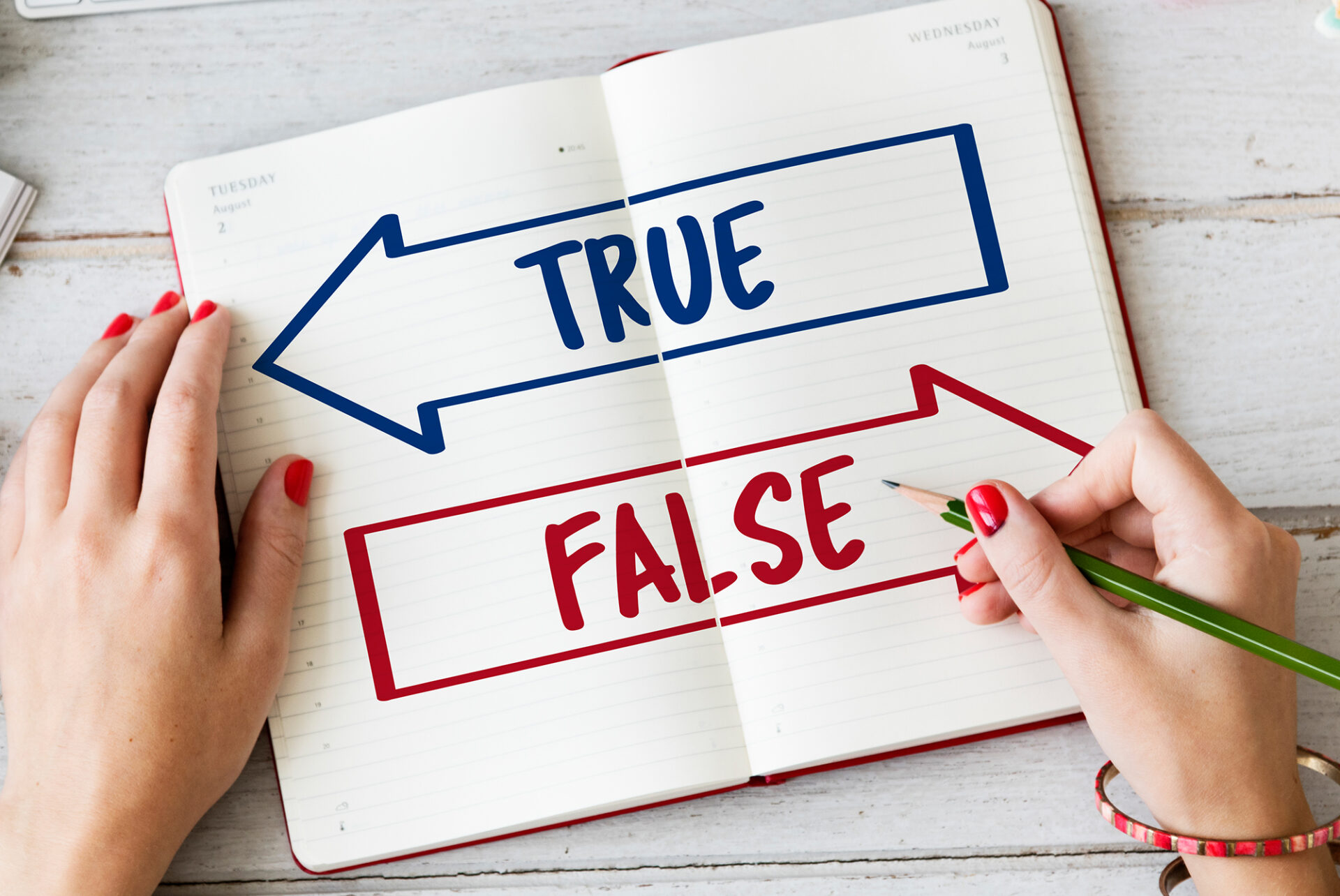
肥満に対する誤解や偏見は、自己管理によるダイエットや治療の妨げになることがあります。
正しい情報を持つことが健康的な体重管理へとつながるので、以下にありがちな誤解とその真実についてご紹介します。
誤解①太っているのは意志が弱いから
「太っている人=意志の弱さ」と決めつけられがちですが、肥満は本人の意志の強さと関係する問題ではありません。
肥満は環境・心理・遺伝などが重なることで起こるため、意志の弱さは原因の1つに過ぎません。
誤解②ダイエットは短期間で効果が出る
無理なダイエットを行えば体重は急激に減少しますが、身体が飢餓状態に陥ることで体重はやがて停滞します。
さらに健康状態を損ねたり、リバウンドのリスクも伴うので、ダイエットにおいて短期間で結果を求めるのは得策ではありません。
体重の3%を1ヵ月の減量目安として行うのが基本なので、健康を維持しつつ、計画性を持って進めることが推奨されます。
誤解③運動だけで肥満が解消できる
運動は肥満解消に必要ですが、消費カロリーを上回るカロリーを摂取していれば痩せることはありません。
また、運動強度を高めれば消費カロリーは増えますが、辛さから持続できずに失敗する可能性は高いです。
したがって、定期的に運動は行いつつ、日々の食事もコントロールすることで、効率的な体重管理ができるようになります。
誤解④肥満は遺伝で決まる
肥満の原因の1つに遺伝がありますが、その影響は約3割ほどと考えられています。
7割が環境要因となるので、両親が太っているからといって子どもが太るわけではありません。
適切な食事や運動などの自己管理によって、肥満の予防は十分に可能です。
誤解⑤肥満は美容上の問題にすぎない
肥満は美容上の問題だけにとどまらず、過剰に蓄積された脂肪は深刻な健康障害を引き起こす可能性があります。
生活習慣病や心血管系疾患など、場合によっては命にも関わるので、太っていることを放置するのは控えるべきです。
肥満についてのまとめ
これまでの内容から、肥満についての重要なポイントをまとめておきましょう。
・肥満は余ったエネルギー(カロリー)の脂肪となって蓄積している状態
・過剰な脂肪の蓄積は生活習慣病や心血管系疾患を引き起こす
・肥満は内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満がある
・BMIや体脂肪率、健康状態によっては「肥満症」という病気として扱われる
・肥満の原因は1つではない(環境、心理、遺伝など)
肥満は見た目の問題だけでなく、健康に深刻な影響を及ぼす可能性がある状態です。
将来にわたって健康を維持するためにも、食事や運動を基本に、必要に応じて肥満治療やメディカルダイエットなども検討して体重をコントロールしていきましょう。
よくある質問
肥満と過体重の違いはなんですか?
肥満と過体重はどちらも体重が基準を超えている状態を指し、WHO(世界保健機構)の基準ではBMI25以上を過体重、BMI30以上を肥満と定義しています。
ただし、日本は海外にくらべ小柄なため、BMI25以上を肥満としています。
肥満が原因となる健康障害はなんですか?
肥満が原因となる健康障害は、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病が代表的です。
また生活習慣病のほかにも、心筋梗塞や狭心症、関節障害など、肥満の影響は全身に及びます。
BMI25を超えていると必ず肥満ですか?
BMIは身長と体重を用いて求めるため、身長に対して筋肉量が多いとBMI25を超えることがあります。
そのためBMIは簡易的な目安の1つと考え、肥満かどうかを判断するには体脂肪率やウエスト径も含めた判断が必要になります。
肥満は病気ですか?
単に肥満では病気ではありませんが、「肥満症」となると病気として扱われます。
肥満症はBMIが25以上であることに加えて、健康リスクや内臓脂肪の蓄積、検査数値に異常が認められる場合に診断されます。